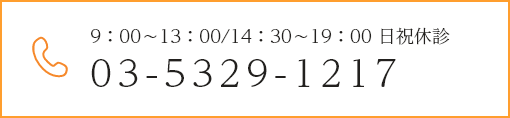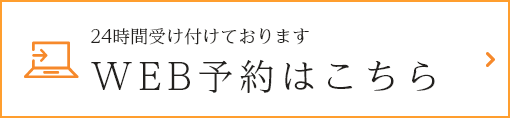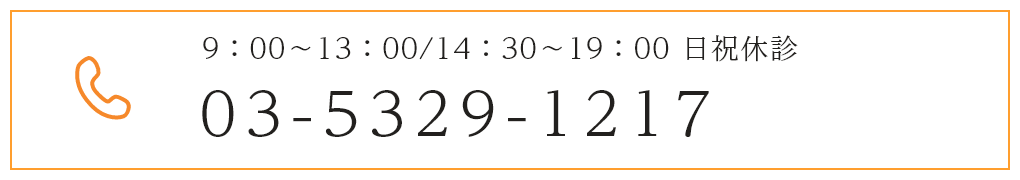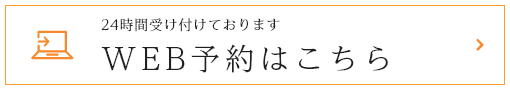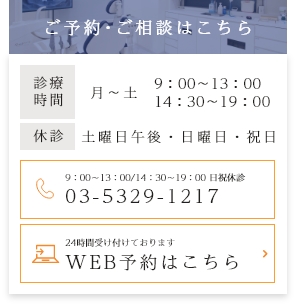No.35 昔むかし・・・
 \ 歯科衛生士のおはなし No.35/
\ 歯科衛生士のおはなし No.35/
”昔むかし・・・”
先日、患者さんと雑談をしていた内容が興味深い話でした。
山形県ご出身のSさんと、数年前山寺へ私が行った話をしていて、
そういえば昔はね‥
人が亡くなると、埋葬される体とは別に歯を小さな骨壷に入れて立石寺まで納めに行ったって、私の大お婆さんの時代の話なんですけどね 理由は知らないんですけどね‥
納める歯が残ってたんだー⁈
この6月に国立科学博物館で「古代のDNAー日本人のきた道」という展示企画に行ってきました。
日本人はどこから来て、今に至る生活になってきたのだろう?
ホモ・サピエンスが日本列島に上陸したのは約4万年前とされているが、今回全身骨格を伴った約2万7000年前の旧石器時代の核ゲノム情報が明らかになった
‥歯が全部ある‼️
目の前の頭蓋骨には、前歯から奥歯まで揃った、顎骨に埋まっている歯が、
私の方を見て神々しく笑っていました。
歯磨きをする行為は飛鳥時代に上流階級で歯木、庶民には、だいたい
1603年江戸時代から爪楊枝のような木を割いたふさ状のものから始まったようです。
約420年前から始まった歯磨き習慣‥
2万7000年前の歯牙の残った人骨‥
もちろん比較する年齢も無関係ではありませんが、現代は早くからご自分の歯を虫歯にしたり歯周病=歯槽膿漏で顎の骨が減少して歯を失うことになる人は多いいです。
砂糖も虫歯の原因一つ、にはなります。
奈良時代からのショ糖、国内生産が始まったのが江戸時代からのようです。
展示場では更に、私がウキウキするような比較を表にしてくれていました。
武家と町人の頭蓋骨と下顎、歯並びまで‼️
武家は『顔が面長』 『鼻が細く高い』 『顎が華奢』 『親知らずが生えてこない』 『乱(らん)杭(くい)歯(ば)である』
町人は『顔が丸い』 『鼻が幅広で低い』 『顎ががっしりしている』 『歯並びがよい』
大名は、武家より更に華奢で現代人に通じるものがあるようです。
江戸時代の町人は一汁一菜だから米を良く咀嚼するしかなかったから顎が育った、ということは大きく関係するでしょう。
約1万3000年続いた縄文時代では、自らの足で狩猟 採集 漁労を幾日も
かけて行い、常に危険を察知しながらの緊張感がありました。
定住生活に進展しながら、山地と海辺でも食材は違い、当然、骨格発達具合も
違いが出ています。
2900年前ころから九州北部から水田稲作が開始されて、弥生時代へ
便利の『べ』の字もなく生きるために行動してきた結果、彼らの骨格 筋肉があったからこそ『硬い食べ物』は、顎の骨や歯を破壊することもありませんでした。
歯磨きなんてしていません。
時代は変化していくのですが、やはりまとめをすると、
祖先のDNAを引き継ぎながら、胎児でも胎盤を通じて良きもの悪きものを受け継ぎ、この世に生まれ落ちてからの育てられ方、自らの作っていく生活環境が、骨格筋肉を作っていき、動かない 歩かない 自分を理解しない食生活 などが、
虫歯や歯周病を作っていく
歯磨きだけでは、それらを予防できないことが改めて理解できました。
便利が悪いとは思いませんが、それに慣れてしまう脳や身体は更に
これからの私たちを病気にしていくことでしょう。
歯科衛生士 野口