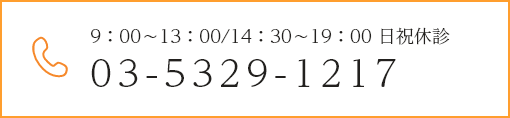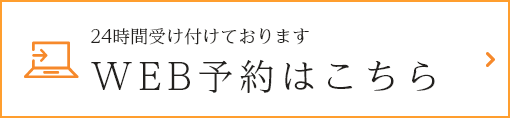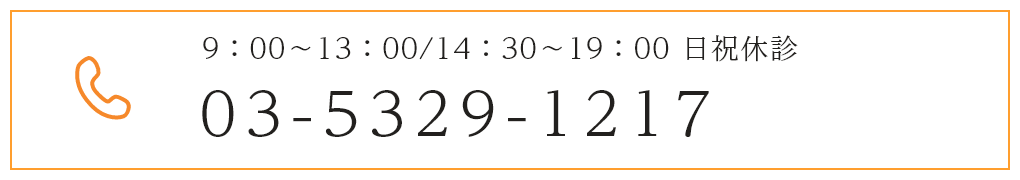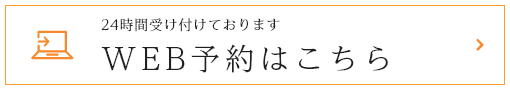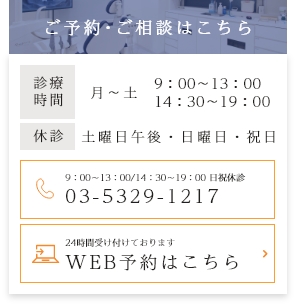No.34 身体の成長には正しい順序があります
 \ 歯科衛生士のおはなしNo.34/
\ 歯科衛生士のおはなしNo.34/
”身体の成長には正しい順序があります”
いきなりですが、『脊髄(せきずい)』とは、脳と繋がり、体の動きや感覚を伝える中枢神経の一部分です。
脊椎(せきつい)(背骨)に保護されながら存在しています。
身体を動かすには、色々な機能が使われるわけですが、脳からの指令で
『脊髄』が身体の隅々、末梢(まっしょう)に命令を出して動きます。
例えば、足を“動かす”のは脳の命令ではありません。
歩きなさいという脳の命令が、腰椎(ようつい)(後に出てくる股関節に通じる)2番に伝わり、すると腰椎2番が「右足を出して、そこから左手出せ」、と頸(けい)椎(つい)(後に出てくる首に通じる)7番に伝わって動き出します。 (かなり専門的ですが難しくてスミマセン)
足を動かすのは、脊髄によるものです。
脊髄と脳は別もので、96%が脊髄の仕事といわれています。
脊髄が正常に発育していれば、例えば座った姿勢で自然と背中は伸びて無意識に維持していられますが、脊髄が発育できていないと背中は丸まったり・頬杖ついたり・足組みしたり・・・崩れていきます。
甥っ子が勉強している背中が丸いので、「下に足着いて背中伸ばして〜」と注意しました。直ったのですが、しばらくみてるとまた姿勢悪くなる。また注意すると、背中伸ばしてお勉強するのですがやがて、
「背中伸ばすの気にすると、勉強が頭に入ってこないっ」と言うのです。
意識して命令出し続けている脳は疲れていきます。
残念ながらこういう使い方で脳は賢くなりません。
卒業式で壇上の生徒が、右手右足両方出てしまう場面は正に、脊髄反射ではなく脳で歩くことを命令し続けている例かと思います。
人はフルに脳を使い続けていると、脳の発達する余裕がなくなります。
無意識に背中を伸ばせる正しく成長した体幹と脊髄反射があれば、脳に余裕ができて賢くなれるのです。正しい脊髄反射がなされていないと、
鉛筆を正しく持てないとか、丸をキレイな円形に描けないとか。
挨拶が反射で出てこないとか。
喜怒哀楽の表情があんまり変化ないとか。
脊髄が正常に発育できていると、無意識に大臼歯の奥歯でモグモグモグモグたくさん噛んで食べ物がドロドロになるまで舌を上顎におしつけながら食べていることができます。これは、疲れません。
顎や歯、首の負荷もない。消化を考えると、胃腸への負担も少なくなり、栄養素は吸収されます。
その構造を考えると、脊髄はとても重要なところです。
生まれて足をバタつかせて発達を始めながら体幹が育ち始めます。生後4か月頃までは床に寝かせたままの時間を見守っていてください。
股関節の一生を決める要因になります。車やベビーカー移動は脊髄発育妨げになります。
育児の専門家は、股関節が定まらないと、上半身をちゃんと動かすことができないと指摘しているそうです。
昨今、前歯しか乳歯が生えてきていないのに固形の食べ物をあげている保護者さんがいらっしゃることに注意をしています。
2歳半で乳臼歯が生えそろったとしても、まだまだ物を砕いてすり潰す機能はありません。
例えば手があっても、指先を使って小さな物をつまめないように。
食べる物を子供にあげる前に、ご自身の口の中で舌と上顎で潰せる硬さなのかどうか、舌で濾して飲み込めるかどうかを試してからお子さんに食べさせてあげてほしいのです。
まだ、飾りの歯を使いだすと、脊髄の通る頚椎を壊します。
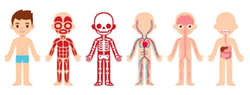
成人しても同様です。
硬い食べ物、コシのある食べ物
【ガム グミ するめ等】は脊柱を壊し脊髄神経に影響を与えます。
正しく発育してこられなかった人ほど、病気として発症するでしょう。
身体はつながっています。
現代を生きる目まぐるしく変化する環境であっても、私たちの身体・DNAは
そうそう変わりません。
取り扱い要注意です。 歯科衛生士 野口
 \ 歯科衛生士のおはなし/
\ 歯科衛生士のおはなし/
”身体の成長には正しい順序があります”
いきなりですが、『脊髄(せきずい)』とは、
脳と繋がり、体の動きや
感覚を伝える中枢神経の一部分です。
脊椎(せきつい)(背骨)に
保護されながら存在しています。
身体を動かすには、
色々な機能が使われるわけですが、
脳からの指令で
『脊髄』が身体の隅々、末梢(まっしょう)に命令を出して動きます。
例えば、足を“動かす”のは脳の命令ではありません。
歩きなさいという脳の命令が、
腰椎(ようつい)(後に出てくる股関節に通じる)
2番に伝わり、すると腰椎2番が
「右足を出して、そこから左手出せ」、と
頸(けい)椎(つい)(後に出てくる首に通じる)
7番に伝わって動き出します。
(かなり専門的ですが難しくてスミマセン)
足を動かすのは、脊髄によるものです。
脊髄と脳は別もので、
96%が脊髄の仕事といわれています。
脊髄が正常に発育していれば、
例えば座った姿勢で自然と
背中は伸びて無意識に維持していられますが、
脊髄が発育できていないと
背中は丸まったり
頬杖ついたり
足組みしたり・・・崩れていきます。
甥っ子が勉強している背中が丸いので、
「下に足着いて背中伸ばして〜」と注意しました。
直ったのですが、
しばらくみてるとまた姿勢悪くなる。
また注意すると、
背中伸ばしてお勉強するのですがやがて、
「背中伸ばすの気にすると、
勉強が頭に入ってこないっ」と言うのです。
意識して命令出し続けている脳は疲れていきます。
残念ながらこういう使い方で脳は賢くなりません。
卒業式で壇上の生徒が、
右手右足両方出てしまう場面は正に、
脊髄反射ではなく脳で歩くことを
命令し続けている例かと思います。
人はフルに脳を使い続けていると、
脳の発達する余裕がなくなります。
無意識に背中を伸ばせる正しく成長した体幹と
脊髄反射があれば、
脳に余裕ができて賢くなれるのです。
正しい脊髄反射がなされていないと、
鉛筆を正しく持てないとか、
丸をキレイな円形に描けないとか。
挨拶が反射で出てこないとか。
喜怒哀楽の表情があんまり変化ないとか。
脊髄が正常に発育できていると、
無意識に大臼歯の奥歯で
モグモグモグモグたくさん噛んで食べ物が
ドロドロになるまで舌を
上顎におしつけながら食べていることができます。
これは、疲れません。
顎や歯、首の負荷もない。
消化を考えると、
胃腸への負担も少なくなり、栄養素は吸収されます。
その構造を考えると、
脊髄はとても重要なところです。
生まれて足をバタつかせて発達を
始めながら体幹が育ち始めます。
生後4か月頃までは床に寝かせたままの時間を
見守っていてください。
股関節の一生を決める要因になります。
車やベビーカー移動は脊髄発育妨げになります。
育児の専門家は、股関節が定まらないと、
上半身をちゃんと動かすことができないと指摘しているそうです。
昨今、前歯しか乳歯が生えてきていないのに
固形の食べ物をあげている保護者さんが
いらっしゃることに注意をしています。
2歳半で乳臼歯が生えそろったとしても、
まだまだ物を砕いてすり潰す機能はありません。
例えば手があっても、
指先を使って小さな物をつまめないように。
食べる物を子供にあげる前に、
ご自身の口の中で舌と
上顎で潰せる硬さなのかどうか、
舌で濾して飲み込めるかどうかを試してから
お子さんに食べさせてあげてほしいのです。
まだ、飾りの歯を使いだすと、脊髄の通る頚椎を壊します。
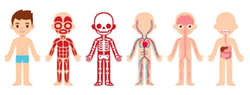
成人しても同様です。
硬い食べ物、コシのある食べ物
【ガム グミ するめ等】は
脊柱を壊し脊髄神経に影響を与えます。
正しく発育してこられなかった人ほど、
病気として発症するでしょう。
身体はつながっています。
現代を生きる目まぐるしく変化する
環境であっても、
私たちの身体・DNAはそうそう変わりません。
取り扱い要注意です。
歯科衛生士 野口